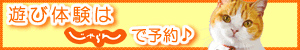開山寂室禅師(正燈国師)

開山寂室禅師
永源寺の開山
開山 寂室元光禅師(じゃくしつ げんこう)諡号:圓應正燈国師(えんのう しょうとう こくし)
寂室禅師は、正応3年(1290)5月15日、岡山県真庭市(旧勝山町)に生まれました。幼名を高麗坊(こまぼう)といいます。父方の家系は、小野宮 藤原実頼(さねより)の末裔であると言われています。
幼少より頭脳明晰で命を尊ぶの念あつく、13歳で出家、東福寺塔頭 三聖寺の無為昭元禅師(むいしょうげん)について寺童となり、15歳で得度、この年、たまたま旅先において一僧の坐禅する姿を見て深く心を打たれ、修行にうちこむようになります。
16歳のとき周囲のすすめで鎌倉禅興寺の約翁徳倹禅師(やくおうとっけん:建長寺開山 蘭渓道隆禅師(らんけいどうりゅう)の法嗣)に入門、わずか一年で約翁の侍者に抜擢されました。約翁は禅師と出会う前夜「天から諸聖が降臨し、光明が山河を照らす」という夢を見たため、禅師に「元光(げんこう)」の名を与えました。
18歳のとき、病床の約翁に「末期の一句」を問うやいなや、面上に一掌をあびせられ、このとき大悟を得ます。
その後も約翁の指導のもと京鎌倉の諸山で修行を積み、東明恵日・東里弘会・一山一寧など中国人僧の教えを受けました。また、相模の律僧 慧雲のもとで具足戒を学びますが、猛勉強によりわずか三ヶ月で行を修めるも床に伏せるほど衰弱し、律師を感心させたといいます。
31歳より7年間、元(中国)に渡航し、元叟行端・古林清茂・清拙正澄・霊隠如芝・絶学世誠・無見先覩・断崖了義・中峰明本などの禅僧を訪ねて教えを受けました。中でも杭州の天目山で隠棲していた中峰明本禅師(ちゅうほうみんぽん)の幻住(げんじゅう)思想――定住せず静かな山中で生涯修行に生きる――に強い影響を受けます。「寂室(じゃくしつ)」の号は、中峰和尚より授けられました。
37歳で帰国されると、以後大寺名刹をはなれ、山中の小庵に身を隠し諸国を行脚されました。その後30年以上におよぶ長い韜晦(とうかい)のご足跡は、西は広島・岡山、東は三河・群馬にまでおよびます。その日々折々に禅師はたくさんの偈頌(げじゅ・漢詩)や手紙を残されました。それら美しい詩の数々は後に『寂室録(じゃくしつろく)』として編まれ、禅師の清廉枯淡な境地をあますところなく伝えるとともに五山文学にも影響を与えました。
71歳のとき、佐々木氏頼に請われ、永源寺を開きます。天龍寺や建長寺へ住持するよう勅書が下されるも固辞し、永源寺にて道風を慕い集い来る修行者の教化につとめました。一説には、この地の風景が中国天目山を想起させたため、永源寺にとどまる決意をさせたとも言われています。
貞治6年(1367)9月1日、78歳にて示寂されました。遺誡(ゆいかい)には「私の死後は建物や寺領を全て領主に返上し、みな山を去ること。大寺に近寄らず、一人ひとりがお釈迦さまの教えを守って修行にはげむこと。しかし、人々が永源寺の存続を強く望むならば、修行の道場として残すのは良い」と遺されています。
応安2年(1368)圓應禅師(えんのう)、昭和3年(1928)正燈国師(しょうとうこくし)の諡号が贈られました。
禅師は書にもすぐれ、現存する多くが重要文化財に指定されています。
寂室禅師の漢詩
『山居』
名利を求めず 貧を憂えず
隠処 山深うして 俗塵に遠ざかる
歳晩 天寒うして 誰か是れ友
梅花 月を帯びて 一枝新たなり
『金蔵山の壁に書す』その二
風 飛泉を撹して 冷声を送る
前峰 月上って 竹窓 明らかなり
老来 殊に覚ゆ 山中の好きことを
死して巌根に在らば 骨もまた清からん